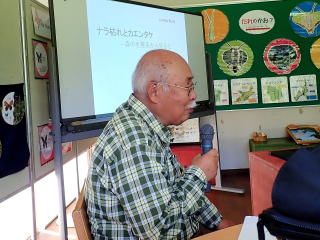ナラ枯れとその後に発生するカエンタケにつては、近年大きな話題になっていますが、その被害と毒性が強調されることが多く、生態系の視点で論じられることはあまりありません。ナラ枯れを森の遷移、森の免疫作用として捉え、カエンタケの発生を森のリサイクルシステムとして解説されました。
観察会では、空梅雨と暑さ続きでキノコの発生が心配されましたが、皆さんの積極的な取り組みにより次々とキノコが姿を現し、新確認種が6種も見つかる充実した観察会になりました。
コロナ禍のなか、暫く講義はお休みでしたが、感染も落ち着いていることもあり、今回再開いたしました。大舘さんの「キノコ入門 1.キノコとは」では、きのこがどんな生き物かについての講義がありました。講義の後はすみれば自然庭園での観察会となりました。観察できた種は地面から出ていたのは
熱心に観察する参加者の皆さん 観察会の後は出合ったキノコの解説
観察会の後はネイチャーセンターに戻り、この日出合ったキノコについて大舘さんの解説がありました。この日出合ったキノコは25種あり、このうち20種の種名が同定されました。その中で、参加者の方から、クロサイワイタケ科と思われるキノコの提出がありました。大舘さんが持ち帰り詳しく調べたところ、採集された方の言われたようにカタツブタケ属のキノコで、種はこの属のタイプのカタツブタケRosellinia
aquila になりました。ただ、この種には近縁種が多くあり、不確定とのことでした。
ヘビキノコモドキ
Amanita spissacea
ハラタケ目 テングタケ科
子実体:ウラベニガサ型で中型。
傘:丸山形→平ら、条線なく、黄褐色の地ををかさぶた状の破片が覆う、
柄:下方に太まり、傘と同様の破片が覆う。
子実層托・幅広く密で、離生。
ヒラフスベ
Laetiporus versisporus
タマチョレイタケ目
ツガサルノコシカケ科
立ち枯れたコナラの樹幹に、白い子供の頭ほどのキノコを発見しました。
子実体:側着型、類球形で、白から淡黄色になり、表面に凹凸がある
子実層托:キノコ全体が褐色の厚膜胞子になる
ムラサキスギタケ
Gymnopilus luteofolius
ハラタケ目 ヒメノガステル科
子実体:キシメジ型で中型。
傘:丸山形→平ら、紫褐色の地を同色の小鱗片が覆う、
柄:上下同径で、膜質のツバがある。
子実層托:密で直生~上生で、黄色。
ヒメカンムリツチグリ
Geastrum quadrifidum
ヒメツチグリ目 ヒメツチグリ科
草地のなかに妙な形のキノコを見つけました
子実体:腹菌型で幼時類球形
基本体:外被が星形に裂開し、中から短柄を持つ内皮に包まれた類球形の基本体が現われ、やがて丁部の孔から胞子を放出する
都内ではあまり見られない稀種
スジウチワタケモドキ
Polyporus grammocephalus
タマチョレイタケ目
タマチョレイタケ科
林内の切り株に、大型のキノコが重生していました
子実体:有柄型で中型
傘:団扇形で、白から淡褐色になる
子実層托:管孔は短く白く孔口は密
カレバキツネタケ
Laccaria vinaceoavellanea
ハラタケ目ヒドナンギウム科
ネイチャーセンターの前の芝生の縁に沿って、毎年姿を現わします。
子実体:キシメジ型~カヤタケ型
傘:丸山形~中央が窪む平ら
子実層托:疎で垂生、紫褐色
柄:中心生で中実
左がカタツブタケで径1~2mm,
右がクロコブタケで径12㎜。
球形で頂部に乳首状の突起があり、
表面黒く微粒状で、肉質は硬い。
世田谷区の住宅街の一角にある”桜丘すみれば自然庭園”は、緑が豊かで多様な生き物が棲んでいます。毎年隔年で夏と秋に”都会のキノコ講座”が実施され、講義と観察会が行われます。長谷川さんの講義「ナラ枯れとカエンタケ」では、近年急速に進行しているナラ枯れと、ナラ枯れの後に発生するカエンタケについて、生態系の視点で解説されました。講義の後は庭園でのきのこの観察が行われ、この日は30℃をはるかに超える猛暑日でしたが、参加者の皆さんは暑さをものともせず、キノコ探しと観察に取り組んでおられました。
観察会後はネイチャーセンターに戻り、今日観察できたきのこについて、長谷川さんの詳細な解説がありました。参加された皆さんは、多くの質問が出るなど、大変熱心に取り組まれ、充実した楽しい講座となりました。今年の講座の観察会は秋でしたが、来年は夏の予定です。夏のきのこの観察を楽しみに、再会を約して散会となりました。
「都会のキノコ講座」 桜丘すみれば自然庭園
2022年7月3日(日) 参加20名
ロウバイシンジョウキン
Rhytidhysteron rufulum
パテラリア目 パテラリア科
その表面に小さな黒い茶碗型のきのこが群生している落ち枝を見つけました。きのこの径は2㎜ほどで、ルーペで見ると、茶碗の縁には条線が並び唇状でした。
ハリガネオチバタケとツルタケの2種のみで、他はすべて材上生のきのこでしたが、全部で20種を観察することができ、しかも、すみればでの新確認種がケガワタケ、トキイロヒラタケ、ウスキニセショウロ、ロウバイシンジョウキンの4種ありました。観察会の後はネイチャーセンターに戻り、長谷川さんの観察できた種の解説がありました。
モチゲチチタケ
Lactarius brunnescens
ハラタケ目 ベニタケ科
林内に淡褐色のキノコが群生していました。傘には強い粘性がありました。
子実体:ベニタケ型で小型
傘:丸山形から平らに開く
柄:中心生で中空
肉:傷つけると白い乳液を多量に分泌し、褐変する
世田谷の住宅街に、それは都会のオアシスのような緑豊かな異空間があります。それが「桜丘すみれば自然庭園」です。緑が豊かで多様な生き物が棲んでいます。隔年で夏と秋に「都会のキノコ講座」が実施されています。
「都会のキノコ講座」はネイチャーセンターで講義が行われます(左)
桜丘すみれば自然庭園でこれまでに観察できた種は、このページTOPからご覧にンれます。
上:胞子 Av.18×7µm
右:子のう先端の構造
ナカグロヒメカラカサタケ
Lepiota praetervisa
ハラタケ目 ハラタケ科
子実体:キシメジ型で小型。
傘:丸山形→中高平ら、白地を暗褐色色の小鱗片が覆う、
柄:下方に太く、膜質のツバがある。
子実層托:密で上生、黄白色。
ニオイクロハラタケ
Agaricus sp.
ハラタケ目 ハラタケ科
子実体:ウラベニガサ型で小型、ヨードホルム臭と黒変性がある。
傘:球形→丸山形→平ら、白地に煤状の鱗片が覆い、触れると黒変する。
柄:白で、淡黄色のツバがある。
子実層托:幅狭く密で離生、白→黒。
ミドリスギタケ
Gymnopilus aeruginosus ハラタケ目
フウセンタケ科チャツムタケ属
森から出ると、芝生に横たわる倒木上に赤褐色のきのこを見つけました。
傘:丸山形から平らに開き、ささくれ状の鱗片があり、緑色のシミが出る。
柄:上下同径で中実、傘と同色で、膜状のツバがある。
ツエタケ
Russula dalbonigra ハラタケ目
キシメジ科ビロードツエタケ属
切り株の根方に、すらりとした姿のきのこが発生していました。
傘:中高の平らに開き、灰褐色で放射状の皺と粘性がある。
柄:根状に伸びて、地中の材に達する。
シロクロハツ
Russula dalbonigra
ハラタケ目ベニタケ科ベニタケ属
次に見つかったのは、クロハツモドキによく似たきのこでした。
傘:丸山形から開いて漏斗型になり、白から次第に黒くなる。アカキツネガサが付き添っていました。
きのこの形状は前種に酷するが、傷つくと赤変せずに黒変する。
クロハツモドキ
Russula densifolia
ハラタケ目ベニタケ科ベニタケ属
森に入って最初に出合ったのは、菌根菌のクロハツモドキでした。
傘:丸山形から開いて漏斗型になり、白から次第に黒くなる。
ヒダ:厚く密で類白色。
肉:傷つくと赤変しやがて黒くなる。
カレバキツネタケ
Laccari vinaceoavellaneaハラタケ目ヒドナンギウム科キツネタケ属
森の道端に出ていたのはまだ傘が開いていない淡紫褐色のきのこでした
傘:丸山形から平に開き、淡褐色で表面胃は凹凸がある。
柄:細長く中実で、傘と同色。
ヒダ:厚く疎で褐色。
10月初旬は秋のキノコの最盛期ですが、猛暑と日照りの影響か、どこの公園もきのこの姿があまり見られず。この日もあまり期待を持たずに観察会に臨みました。ところが、さすが自然豊かなここすみれば自然庭園、森に入るや数種類の菌根性のキノコに出会うことができました。
世田谷区の住宅街の一角にある”桜丘すみれば自然庭園”は、さほど大きな公園ではありませんが、緑が豊かで多様な生き物が棲んでいます。毎年、隔年で夏と秋に”都会のキノコ講座”が実施され、講義と観察会が行われます。今年の講義は大舘さんの「きのこの生きかた」で、きのこの養分摂取のしかたと、その生態系での役割について話されました。講義の後は園内でのキノコ観察で、20種ほどのキノコを観察することができました。観察会の後は、長谷川さんによる当日観察できたキノコの解説がありました。
「都会のキノコ講座」 桜丘すみれば自然庭園
2023年10月1日(日) 参加25名
ウスキニセショウロ
Scleroderma flavidum
イグチ目 ニセショウロ科
林内の地上に腹菌型のきのこが数個発生していました。薄黄色で表面には糠状の鱗片があり、基部には白い菌糸束が見られました。切断するとグレバは黒く成熟していました。このきのこは有毒ということです。
桜丘すみれば自然庭園でこれまでに観察できた種は、このページTOPからご覧にンれます。
トキイロヒラタケ
Pleurotus djamor
ハラタケ目 ヒラタケ科
廃材置き場には多くの腐生菌が発生していました。多くはサルノコシカケ類のきのこですが、なかに大型のヒラタケ型で、乾燥して淡くなってはいましたが朱鷺色が残るきのこがありました。
新宿御苑・森林公園に続き、今年の講座も3回目になりましたが、快晴と猛暑は相変わらずで、今回もきのこの探しに苦労する観察になりました。そんなキノコにとっての悪条件にもかかわらず多くのかたが参加され、講義に観察に熱心に取り組まれました。
コキララタケ
Coprinellus pdomesticus
ハラタケ目 ナヨタケ科
朽ちた材を黄色い菌糸がマット状に覆い、その中に小さなキノコが出ていました。
子実体:クヌギタケ型
傘:円錐形で、表面を白く細かい鱗片が覆う
子実層托:白いヒダがやがて黒くなり液化する
ウラムラサキシメジ
Tricholosporum
porphyrophyllum
ハラタケ目 キシメジ科
林に入ると形のよいキノコが見つかりました。ヒダが美しい紫色のキノコです。
子実体:キシメジ型
傘:丸山形で黄褐色
子実層托:幅狭く密で紫色
柄:中心生で中実
ニオイクロハラタケ
Agaricus sp.
ハラタケ目 ハラタケ科
林内の落ち葉の中に灰色のきのこが並んでいました。近寄ると強い薬品臭がしました
子実体:キシメジ型
傘:丸山形で灰褐色、表皮がひび割れる
子実層托:白から暗褐色になる
柄:上下同径で、膜状のツバがある